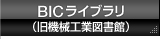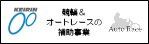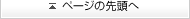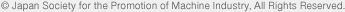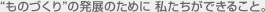研究会・イベントのご報告 詳細
「モノづくり中小企業における「両利き経営」の特質と実践―統計分析によるユニークなファインディングス―」
| 主催:(一財)機械振興協会経済研究所主催 第483回機振協セミナー「モノづくり中小企業における「両利き経営」の特質と実践―統計分析によるユニークなファインディングス―」開催報告 オンデマンド配信終了 | |
|---|---|
| 開催日時 | 2025年4月22日(火)14:30~16:00 |
| 場所 | WEBシステムにより開催(Zoom) |
| テーマ | 「モノづくり中小企業における「両利き経営」の特質と実践―統計分析によるユニークなファインディングス―」 |
| 講師 | 講師:京都大学経営管理大学院 特定准教授 機械振興協会経済研究所 特任研究員 國分 圭介氏 モデレーター: 機械振興協会 理事 兼 経済研究所 所長代理 北嶋 守 |
| 内容 |
2025年4月22日(火)にWebシステムより、第483回機振協セミナー「モノづくり中小企業における「両利き経営」の特質と実践―統計分析によるユニークなファインディングス―」を開催しました。講師は、京都大学経営管理大学院特定准教授・機械振興協会経済研究所特任研究員の國分圭介氏にお願いしました。またモデレーターおよび調査研究事業の概要説明は機械振興協会理事兼経済研究所所長代理の北嶋守が務めました。当日は、76名にオンラインでご参加いただきました。ご参加いただきました皆様に、厚く御礼申し上げます。【講演内容】本講演では、スタンフォード大学のチャールズ・オライリー教授が提唱した「両利きの経営」の概念を参考に「両利き経営」という独自の概念を設定し、モノづくり中小企業における両利き経営の特徴と実践に関する分析を行った。両利き経営とは、主力事業の絶え間ない改善(知の深化)と新事業に向けた実験と行動(知の探索)を両立させる経営戦略である。本講演の冒頭では、両利き経営の概念や調査研究委員会の概要に関してモデレーターの北嶋守が説明した。 続いて、講師の國分圭介氏が、両利き経営に係る先行研究から、深化への偏重は成功の罠に陥りやすく、探索への偏重は失敗の罠に陥りやすいことから、深化と探索のバランスが重要であることが指摘されてきたことを説明した。しかしながら、大企業と異なり、中小企業では深化と探索の両方に限られたリソースを振り分けることが難しい。さらに、日本の事情として、プロダクトイノベーションを実現した企業の比率は低く、中小企業は既存のサプライチェーンの中で大企業を求めるスペックの製品や部品を供給することに重点を置いてきたため、自社の強みやコア技術を上手く認識していない企業は多く課題がある。 このような課題の解決策として、①情報取得(オープンイノベーション)②ICTの活用(デジタルトランスフォーメーション)③脱炭素経営の実践(エコイノベーション)に着目した。先ず、情報取得では、リソースが乏しい中小企業でも外部にある知識にアクセスすることで、市場への柔軟性を高めることに役立つと考えられる。またICTは、市場の変化にタイムリーに対応しデータ収集・処理を強化し、知識の探索と活用の速度を向上させることに繋がるとされる。最後に脱炭素経営は、日本でも中小企業の25%強が取引先からの要請を受け、国内外でサプライチェーン全体の脱炭素化が加速している。 その上で、経済研究所では令和6年度に、社内環境の整備や情報取得、ICTの活用、脱炭素経営の実践がどのように企業の深化と探索、パフォーマンスに影響しているかについて独自のアンケート調査を行なった。その結果、パフォーマンスに対しては両利き経営(深化と探索)と深化を進める経営が高い相関を示している(有効である)こと、市場の変化が大きい企業や社内環境の整備、展示会などでの情報取得、ICTの活用、脱炭素経営の実践に積極的な企業ほど両利き経営が進む傾向にあることがわかった。また、取引先からの情報収集に依存する企業は深化に特化する傾向にあり、専門家からの情報取得は探索・深化ともに下げる結果となった。なお、自由回答では、新規需要で開拓した顧客の要求への対応の難しさ、新規事業を行うための社員のモチベーション不足、新規事業を行うための社員への情報周知の不足、グローバル化や情報化環境意識の高まりへの対応の難しさ、新規事業に振り向けるためのリソース不足、設備の老朽化に伴うコストアップ、そして人材不足が課題として挙げられた。 以上の結果から、本講演の最後では、日本のモノづくり中小企業における両利き経営の特徴には海外の事例とは異なり、深化と両利き経営の両方がパフォーマンスを高める構造があり、理想と現実の間で妥協点を見出すことが重要であることや、公的支援機関の支援策として現場の課題に寄り添う支援を行い、専門家からの支援に対する悲観的な見方を払しょくすることが求められていることを指摘した。 その後、モデレーターで本調査研究のPLの北嶋守から、調査研究成果を基に作成した『モノづくり中小企業のための「両利き経営」の手引き』が紹介され、日本のモノづくり中小企業の「両利き経営」では、「知の深化」、「知の探索」に加えて、外部資源を活用した「知の補完」が重要である点が報告された。 講演後は質疑応答が行われ、両利き経営を行っているモノづくり中小企業の事例やアンケート調査の地域の選択理由、公的機関の具体例に関する質問の他、中小企業が両利き経営を実践する際に経営支援不足を補うための方法について議論がなされ、盛況裏に終了した。 動画の配信・資料の掲載は終了いたしました。 |